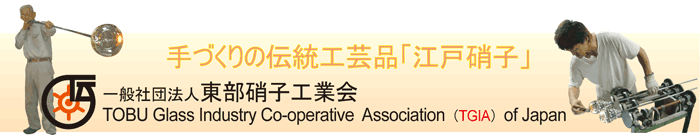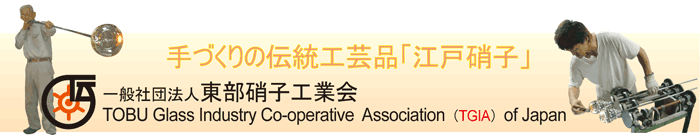|
|

『日本のガラス/江戸時代』
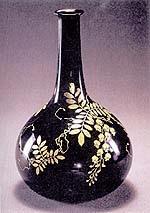
紫色藤蒔絵徳利 江戸時代

藍色ちろり 江戸時代
(サントリー美術館)

江戸ガラス 切子蓋付碗
|

|
しばらく製造が途絶えていた日本のガラスづくりは、16世紀後半から17世紀前半にかけて、中国
人または南蛮人、紅毛人によって長崎の地に上陸し、大阪、京都、江戸などに伝わっていった。
元亀元年(1570)、肥前国の大村藩主・大村理博が長崎港で海外との貿易を開いた。同年にポルト
ガル人が長崎にガラス工場を建て、天正元年(1573)にはオランダ人がガラスの製法を日本人に伝
え、江戸時代に入って寛永年間(1624〜1643)には中国のガラス工が長崎に来てガラスの製法を伝
えたという。
享保5年(1720)刊行の『長崎夜話草』によると、長崎の商人・浜田弥兵衛は元和年間(1615〜1623)
に海外に渡り、外国の商況を視察するかたわら眼鏡の製法を習得し、帰国後にその技法を生島藤
七に伝えた。生島藤七はその後、南蛮人のガラス工が来たときも技法を学び、ガラスの念珠、巻
軸、灯篭、簾などを造ったので、"多麻也"と呼ばれたという。
また、延宝4年(1676)に長崎の豪商・末次平蔵・茂朝の密貿易が発覚し、その財産を没収した長
崎奉行所の記録『末次平蔵関所家財道具御払帳』の中に、「日本物びいどろ釣花一つ」という記
述があり、この頃にはガラスが製造されていたことがわかる。
近世日本のガラスはいつ、どこから伝わった製法が伝承されていたかを検証すると、当時の日本
製のガラスは中国系のカリ鉛ガラスで、ヨーロッパ系の鉛を含まないカリ石灰ガラスではないこ
とから、元亀元年より以前に中国の製法が伝えられたという説が有力であると思われる。当時の
ガラスは、古来からの「玻璃」「瑠璃」とともに、ポルトガル語からの「ビードロ」、オランダ
語からの「ギャマン」などと一般には呼称されていた。
|
【近世「江戸時代」のガラスづくり】
宝暦元年(1751)、長崎の商人・播磨屋(久米)清兵衛は大阪に移ってビードロの製造を始め、これ
が大阪ガラスの始祖といわれている。一方、江戸のガラスは…といえば、文政13年(1830)発行の
『嬉遊笑覧』によると、「今も浅草に長島屋半兵衛という硝子(びいどろ)氏あり、歳70余なり。
この養父を源之丞といふ。江戸にて硝子(びいどろ)を吹き始めたるはこの者なりといへり。かれ
これ考へてみればその始め正徳のころにやあらん」とあり、正徳年間(1711〜1715)にガラス造り
の技術が江戸に伝わったことを記している。
そして明和7年(1770)刊行の『職人部類』には、当時すでに江戸でガラスが製造されており、ガラ
ス製品の種類も多くなったとしている。しかし、江戸ガラスの祖といわれているのは加賀屋の皆
川久兵衛と上総屋の在原留三郎で、江戸・日本橋通塩町で金属丸鏡と紐付眼鏡を製造・販売して
いた加賀屋は、文政年間(1818〜1829)にガラス製造を計画して手代の文次郎(のち久兵衛に改名)
を大阪に送り、播磨屋から独立した和泉屋嘉兵衛のもとで数年間修行させ、江戸に帰ってガラス
製造を行った。
皆川久兵衛は天保10年(1839)に加賀屋から分家して独立、加賀屋久兵衛、通称「加賀久」と名乗
り、大伝馬町に店を構えてガラス製造・販売を始めた。加賀屋久兵衛は、天保5年(1834)に金剛
砂でガラス面に彫刻し、切子細工を工夫したと伝えられている。また、理化学用・医療用ガラス
を日本で始めて製造したことでも知られている。
一方、上総屋の在原留三郎は、文政2年(1819)に浅草・南元町に工場を設け、かんざしや風鈴など
を製造・販売していたが、文政11年(1828)から天保5年(1834)まで長崎で修行を積み、再び江戸に
帰ってかんざしや風鈴などの製造を続けた。また、安政年間(1854〜1859)には蘭学者・川本幸民
の門人から依頼を受け、蒸留器付属のレトルトを製作したといわれる。
この「加賀久」皆川久兵衛と「上総屋」在原留三郎の二人は、江戸から東京に時代は変わっても
ガラス業界のリーダーとして活躍し、その二代目は、現在の一般社団法人東日本硝子工業会のルーツ
になる「東日本玻璃製造人組合」の発起人になっている。江戸において、ガラス生地を製造・加
工していたのは加賀久と上総屋くらいで、一般には種屋といわれ、他のガラス製造業者はその種
屋から餅種としてガラスを購入し、これを再溶解して製品化していた。幕末当時、主なガラス製
造業者は、福田八十二(浅草総泉寺門前)、伊勢屋儀作(芝神明町新道)、小山清兵衛(芝神明前三島
町)、大隈源助(浅草茅町2丁目)であり、そのほか江戸ではアイヌ玉も造られていて、アイヌの女
性には玉類が欠かせない装身具として重宝されていたので、江戸で造られたトンボ玉などが数多
く蝦夷地に渡ったといわれており、浅草清島町・松前藩の屋敷には王仁というトンボ玉つくりの
名人が召抱えられていたという。江戸時代に、ビードロ師またはギャマン師と呼ばれたガラス製
造業者は、その製造技術を高く評価され、工場の設立、原料の購入などに格別の便宜を与えられ、
なかには扶持を与えられ帯刀を許される者もあった。
また、後に有名になる薩摩ガラスは、弘化3年(1846)に加賀久の従弟で江戸・芝源助町の四本亀
次郎を、薩摩藩主・島津斎興がガラス工場を開設するにあたり招いたのが始まりになる。ただ、
その薩摩ガラスは島津斎彬の没後、藩政の建て直しのため工場は縮小され、ガラス職人の多くは
江戸に移住していった。
安政6年(1859)、日米修好通商条約締結により横浜、神戸などの開港とともに、西洋文明が輸入
されるようになったが、なかでも石油ランプは夜を明るく照らし急速に普及していった。当時の
舶来品のうち、石油ランプと石油が最高の輸入額を記録していることからも、その普及率の高さ
を知ることができる。それまで風鈴や玉などを製造していたガラス業者は、輸入に頼っている石
油ランプを見よう見まねで製造するようになり、明治維新直前の慶応2年(1866)には、大阪の久
米庄兵衛、伊藤庄三郎らがランプの製法を研究、苦心して造るようになり、東京でも加賀久、上
総屋などホヤを製造できるようになり、やがて油壺やバーナーなども国産化できるようになった。
≪前へ戻る 次へ進む≫
|
|