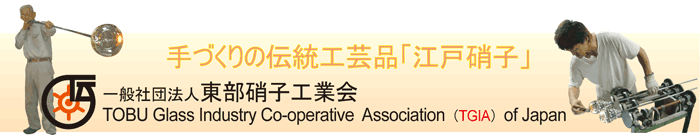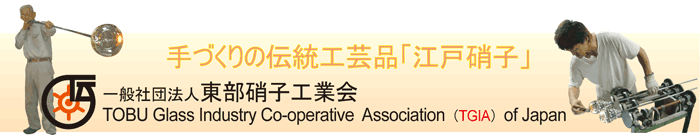|
|

『日本のガラス/古代〜中世』

弥生時代のガラス玉・鉄製鎌
さいたま市指定有形文化財
|

|
日本でのガラス製造を見ると、岡山市の弥生時代後期(2〜3世紀)鹿田遺跡でガラス工房跡が発見
されており、この頃すでにガラスの製造を行っていたものと思われる。しかし、この頃のガラス
は原料を調合・溶解して造られていたものか、他国から渡来したガラス製品を溶解して造られて
いたものかは、これらの遺跡調査からは明らかにされていない。
古墳時代(3〜6世紀)には、勾玉(まがたま)、角型きりこ玉、とんぼ玉、腕輪などのガラス製品が
造られ、飛鳥時代(6〜7世紀)、奈良時代(7〜8世紀)には朝廷の保護のもとでガラスは製造され、
玉類のほかに仏教に関係する用途に多く使われ、天平6年(734)の正倉院の「造仏所作物帳」の断
簡には、ガラス種を造る原料や着色料、その他のことが記録されており、この頃にはガラス種か
ら造ることができるようになって、盛んに造られていたようだ。
それが平安時代(8〜12世紀)になると、風俗の変化、磁器製品の発達、承平天慶の乱(935〜941)
などの影響があってか、大宝律令の官位令でガラスを司ると規定されていた「典鋳司(いものでの
つかさ)」によるガラス製造は途絶することになった。そのため、平安時代から鎌倉、室町時代に
かけて、日本で製造したといわれるガラス製品は非常に少ないが、仏像の瓔珞や台座の飾りには
ガラス玉が多く使われているので、ガラス製造は朝廷から民間に代わって、細々と続いたものと
推測される。しかし、それも継続されることはなく、室町時代末頃に日本のガラス製造は完全に
途絶えてしまった。
この頃のガラスは、大陸から渡来した「玻璃(はり)」または「瑠璃(るり)」と称されており、明
治中期まで一般的な呼称になった。この言葉は、梵語あるいは中央アジアの言語が語源だとされ
ている。
|
≪前へ戻る 次へ進む≫
|
|